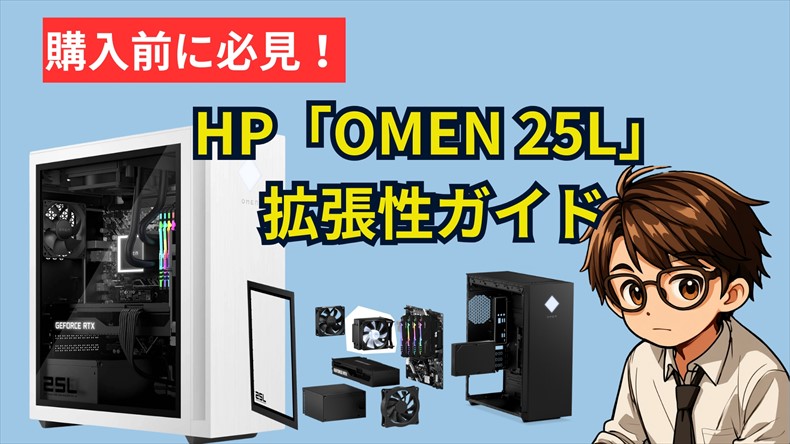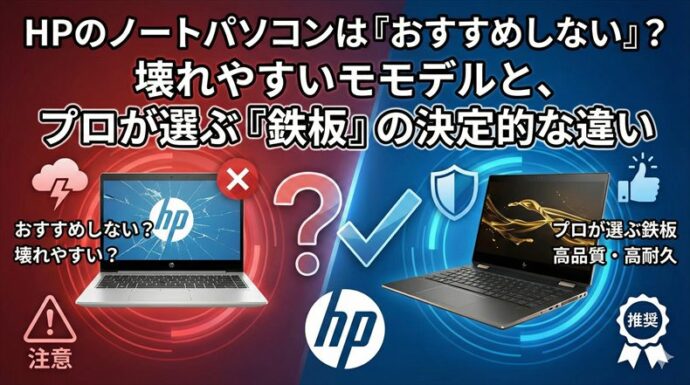「OMEN 25Lって拡張できるの?」
そんな疑問を持った方へ。
実は、OMEN 25Lは「ある程度までは拡張できるけれど、なんでもできるわけではない」という、ちょっとクセのあるPCです。
しかも、型番や世代によってメモリ規格やストレージスロットの数が違うため、拡張の前に“確認すべきポイント”が多いのも特徴です。
OMEN 25Lは完売終了⇒後継機はこちらから>>>
このページでは、
- OMEN 25Lはどのパーツが拡張しやすいか
- OMEN 25Lどんな制約があるのか
- OMEN 25Lの自分に合った使い方はどれか
を、図解・判断ポイント・構成例付きでわかりやすく解説します。
「あとでグラボを変えるかも」「外付けHDDで運用すべき?」と迷っている方も、この記事を読めば自分にとって最適な選び方が見えてきます。
まずは、自分のPCの型番とスペックを確認してから読み進めてみていただくと良いと思います。
\スペック拡張性を詳しく見る/
OMEN 25L位置づけ
OMEN 25Lは、HP(ヒューレット・パッカード)が展開するOMENシリーズの中でも“ミドルクラス〜エントリー上位”に位置づけられるモデルです。
OMEN 25L位置づけをわかりやすく整理すると
| モデル名 | 容量 | 拡張性 | 冷却性能 | 静音性 | 主な用途 | 想定ユーザー層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEN 25L | 小型(25L) | 必要最小限 | 標準 | やや静か | ゲーム/日常利用 | 初〜中級者/コスパ重視派 |
| OMEN 40L | 中型(40L) | 中程度 | 高め | 標準 | ゲーム/動画編集 | 中級者〜 |
| OMEN 45L | 大型(45L) | 高い | 非常に高い | 高負荷対応 | ハイエンドゲーミング/配信 | 上級者/拡張前提派 |
| OMEN 25L パフォーマンスダッシュモデル(第14世代 Core™ i7)スペック表 | |
|---|---|
| OS | Windows 11 Home |
| プロセッサー | 第14世代 インテル® Core™ i7-14700F |
| メモリ | Kingston FURY 32GB(16GB×2)DDR5-5200MHz(Intel® XMP対応、RGB) |
| グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Super |
| ストレージ | Western Digital WD_Black 1TB M.2 SSD(PCIe Gen4×4 NVMe) |
| 冷却方式 | 3ヒートパイプ空冷クーラー(サイドフロー・RGB) |
| カラー | シャドウブラック |
| 光学ドライブ | なし |
| 無線機能 | IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)、Bluetooth 5.0 |
| マウス・キーボード | 付属なし |
| 保証 | 1年間(引き取り修理、パーツ保証、電話サポート) |
| オフィスソフト | なし |
| モニター | なし |
| その他 | 記載なし |
特徴まとめ:OMEN 25Lはこんなモデル
- 特徴1:スタイリッシュでコンパクト
- サイズ重視の人にとって扱いやすい設計。
- 省スペースな場所にも設置可能。
- 特徴2:最低限の拡張性
- メモリ・M.2 SSD・一部ファンなど“最低限”の拡張に対応。
- ただし、電源交換やGPUの大型化には制約が多い。
- 特徴3:冷却設計と静音性は平均的
- 軽〜中負荷のゲームであれば問題ないが、発熱の高い作業には不向き。
- 特徴4:価格と性能のバランスが良い
- 同スペック帯では価格が比較的抑えられており、コスパ重視ユーザーに人気。
OMEN 25Lをおすすめする人しない人
| OMEN 25Lが向いている人 | OMEN 25Lが向いていない人 |
|---|---|
| 初めてゲーミングPCを買う人 | 将来、大型GPUや高性能冷却を追加したい人 |
| あまりパーツを触らず、必要な分だけ拡張したい人 | 多数のストレージやPCIe拡張カードを搭載したい人 |
| 省スペース+そこそこの性能で満足できる人 | 電源やCPUクーラーの交換を積極的に考えている人 |
| 「今はこのまま、将来は外付けで足す」スタイルに納得できる人 |
【結論】OMEN 25Lの拡張性は“必要最小限”?用途と予算で最適解を選ぶべし
まずは、OMEN 25Lの拡張性の全体像と、最初に考えるべきポイントを整理します。
【結論】OMEN 25Lは、基本的な拡張ができる最低限の余地を持つモデルです。
ただし拡張性に過度な期待を持つと、ケース内の制限や電源設計の都合で不満が出やすくなります。
 Risa
RisaOMEN 25Lは「今必要な性能+α」には最適ですが、「後から色々拡張したい」人には少し物足りないかもしれません。
OMEN 25Lは、拡張前提ではなく「完成品+α」で十分な人向けの高コスパモデルです。
一方で、パーツ交換や内部の自由度を重視するなら、40Lや45Lのほうが結果的に満足度が高くなるケースもあります。
\ HPダイレクトで /
拡張性を求めるなら、まず「どこができて、どこが無理か」を知ることが重要です。
また、今すぐ必要な性能と将来に向けた余地、どちらを重視するかで選ぶ構成も変わります。
- 何が増設できて、どこに限界があるかを最初に把握する
- 増設できる部分と限界を把握
- 今すぐか将来か優先度で判断
何が増設できて、どこに限界があるかを最初に把握する
OMEN 25Lは、部分的には拡張が可能ですが、内部スペースや電源構成に制約があります。
増設に向いているパーツと、制限が大きいパーツを最初に見極めておくと無駄がありません。
- 拡張できる:メモリ、M.2 SSD、ケースファン
- 拡張は条件付き:GPU交換、CPUクーラー
- 拡張は非推奨:3.5インチHDD複数、電源交換、PCIe拡張
たとえば、メモリとM.2は空きスロットがあれば手軽に増設できます。
一方で、GPU交換はサイズや電源容量の条件をクリアしないと難しくなります。
3.5インチHDDはベイが限られており、2台以上の内蔵は非現実的です。
PCIeスロットも物理的に空いていても、配線や冷却で実用性が下がることがあります。
電源交換はシャシーの構造やメーカー保証の観点から推奨されません。
まずは、「何を足せるか」よりも「何が制限されるか」を確認するのが正しい順番です。
拡張したい内容によって、OMEN 25Lが合うかどうかが自然と見えてきます。



できること・難しいことを最初に整理すれば、後悔のない選択ができます
OMEN 25Lの拡張ポイント「今すぐ必要」vs「将来の拡張」どちらを優先?
パーツを増やすかどうかは、使い方とタイミングで判断が変わります。
「今快適にしたい」のか、「将来の性能確保を優先したい」のかで選ぶべき拡張が変わります。
OMEN 25Lは、最初の構成がよければそのまま快適に使える設計です。
しかし、後からGPUや電源を変えたい人は、設計上の余裕が足りなくなる可能性があります。
- 今すぐ快適→M.2 SSD追加
- ゲーム性能強化→メモリ増設
- 静音性重視→ケースファン追加
- 将来のGPU交換→電源とスペース確保
- 高負荷用途→冷却と排熱対策
ゲームのロード時間を短くしたいなら、今すぐM.2 SSDを増設するのが効果的です。
静音性を求める人は、ケースファンの追加で風量と音を調整できます。
将来4K高画質ゲームやVRを考えているなら、今のうちに電源容量とクリアランスを確認しておきましょう。
電源に余裕がないと、高性能GPUへの交換時にボトルネックになります。
また、ケース内のスペースが狭いと長いグラボが物理的に入らないこともあります。
今すぐ使うための拡張と、将来に備える拡張は違うものだと割り切って設計しましょう。
全体のバランスを考えながら、今と未来の優先順位を自分で決めることが大切です。



今すぐの快適さと将来の安心、どちらを優先するかがカギです
事前チェック:型番・世代・電源・クリアランス
OMEN 25Lは、同じ見た目でも型番や世代によって仕様が微妙に異なります。
事前に自分のPC構成を正確に確認しないと、パーツ選びでミスが起こりやすくなります。



型番・電源・スペースをしっかり把握してからじゃないと、せっかくのパーツが無駄になりますよ。
- 型番・世代で規格が変わる
- 電源容量とコネクタ形状を確認
- GPUサイズと配線の物理空間を測る
ここでは、増設や交換を検討する前に必ず確認しておきたい3つの事前チェックポイントを解説します。
この段階でミスを防げば、その後の拡張計画がスムーズに進みます。
型番(GT15など)と世代で変わる規格(DDR4/DDR5・M.2本数・I/O)
OMEN 25Lは同じモデル名でも、販売時期や構成によって内部規格が違う場合があります。
まず最初に、自分のPCの「型番」と「世代(発売年)」を正確に確認しましょう。
- 本体シールのGT15などの型番を見る
- システム情報でプロセッサやチップセットを確認
- メモリはDDR4かDDR5かをチェック
- M.2スロットの数と空き状況を確認
- USBポートや映像端子の種類と位置
型番は本体の背面や底面に貼られたシールから確認できます。
GT15、GT12などの英数字が、モデル構成を見分けるヒントになります。
Windowsの「システム情報」からCPU名を見れば、世代が大まかに把握できます。
メモリ規格(DDR4/DDR5)や、M.2の数・位置・空き状況も合わせてチェックが必要です。
背面のUSB端子や映像出力(HDMI/DisplayPort)の数や位置も、拡張計画に影響します。
型番と世代で違いが出るので、増設前に必ず現物で確認しましょう。
間違った規格のメモリやSSDを買ってしまうミスを避けられます。



まずは型番と規格をメモすることから始めよう
電源容量とコネクタ(8pin/12VHPWR)の有無
GPUや冷却パーツを強化したい人は、電源ユニットの性能を事前にチェックしましょう。
「使える電力量」と「接続できるコネクタ」が拡張の成否を分けます。
- 電源容量(W数)を確認する
- 8pin・6pinなど補助電源の形状
- 12VHPWRの有無と位置
- 電源の合計出力とレール構成
- 安全マージンを20?30%取る設計
電源の定格出力は、ラベルか仕様書で確認できます。
追加GPUが必要とする電力より、常に20?30%上の余裕を持たせるのが安全です。
12VHPWRコネクタ(新型の補助電源)があるかどうかも要チェックです。
変換ケーブルを使う場合も、配線の曲げや負荷に注意しないと発熱リスクがあります。
電源は「足りるかどうか」だけでなく、「安定して使えるか」まで考えて選びましょう。
電源の質と余裕は、拡張の土台になります。



電源は“ギリギリ”ではなく、“ちょい余裕”が鉄則
GPU長さ・厚み、ケーブル取り回しの物理余裕
グラボを交換したい人は、まず物理的なスペースの確認が必要です。
特に長さ・厚み・ケーブルスペースの3点が干渉の原因になりやすいです。
- GPUの長さとケースの奥行き
- 2.5スロット or 3スロット厚み
- ケーブル曲げスペースの確保
- ストレージブラケットの位置
- フロント配線との干渉
たとえば、3スロット厚のグラボは幅が広く、排熱が隣のスロットに影響します。
長さがあるGPUは、ストレージブラケットや前面の配線にぶつかることがあります。
補助電源ケーブルは、グラボに差してから少し余裕を持って曲げる必要があります。
このとき、ケースとの距離が近いと、無理な曲げになって断線や熱の原因になります。
ケース内部を定規で測って、使いたいGPUの寸法と比べるのが確実です。
スペースが厳しい場合は、より短め・薄めのGPUを選ぶ必要があります。



グラボの交換前に“物理の壁”を測ろう
拡張の可否・優先度の早見
OMEN 25Lで拡張を考えるとき、全てのパーツに手を出すのは現実的ではありません。
まずは、費用と手間に対して効果が高いものから順に取り組むのがポイントです。



コスパがいいパーツから順に手を付けましょう。優先度を見極めるのが賢い選び方です。
- メモリ・ストレージの追加は低コスト高効果
- GPU交換は条件付きで中コスト
- 電源やI/O拡張は難易度とリスクが高い
この見出しでは、各パーツの拡張について「効果」「難易度」「リスク」の3軸で優先度を整理します。
あらかじめ判断基準を持っておくと、無駄な買い替えやトラブルを避けられます。
メモリ/ストレージ(M.2・2.5/3.5インチ)?比較的容易
OMEN 25Lで最も手軽に拡張できるのは、メモリとストレージです。
効果に対して手間が少なく、コストも抑えられるため、最初に検討すべきポイントです。
- メモリはデュアルチャネルで効果大
- M.2 SSDは高速・省スペース
- ヒートシンクで発熱対策が必要
- 2.5インチはケーブルの確認を
- 3.5インチは1台限定と考える
メモリは空きスロットを活用すれば、デュアルチャネルで処理速度が体感で向上します。
M.2 SSDは高速で取り付けも簡単ですが、発熱による性能低下を防ぐためヒートシンクが有効です。
2.5インチSSDの増設には、SATAケーブルと電源ケーブルの確認が必要です。
3.5インチHDDは取り付けスペースが1台分しかないケースが多く、外付けに頼るのが現実的です。
いずれも比較的簡単に対応でき、使用感の改善にもつながるため、優先度は高いと言えます。
まずは空きスロットとケーブルの有無を確認して、無理なく追加できる構成を選びましょう。



最初に手を入れるならメモリかM.2がコスパ最強
GPU交換?サイズ・電力・発熱の条件付き
GPU交換は効果が大きい一方で、サイズ・電源・熱対策といった条件をクリアする必要があります。
特にOMEN 25Lはシャシーが小さいため、物理的な干渉や冷却問題が起こりやすくなります。
- GPUの長さと厚みに注意
- 電源容量が足りるか確認
- 補助電源の本数・形状を確認
- 吸排気の風の流れを確保
- 熱と騒音が増える点に注意
OMEN 25Lでは、3スロット級の大型GPUを入れるのはかなり厳しく、長さの制限にも注意が必要です。
また、高性能GPUは補助電源が複数必要なことが多く、電源ユニットのスペック確認も欠かせません。
吸気・排気の流れを遮らないように設置できるかも、温度管理の重要なポイントです。
性能向上の期待は大きいですが、物理的・電力的な制限があるため、無理のない選定が求められます。
GPU交換は効果は高いものの、相性ミスのリスクもあるため、事前確認が最重要です。



GPU交換は高効果。でも「通るか・動くか」が勝負
冷却(ケース/CPUファン)?取り付け位置と騒音のバランス
冷却の強化は静音性と温度安定に効果がありますが、取り付け位置やバランスを考える必要があります。
とくにファンの回転数やエアフローの方向で、冷却効率と騒音が大きく変わります。
- 吸気と排気の位置を整理
- ケースファンの厚みを確認
- CPUファンは高さ制限あり
- 正圧・負圧のバランスを見る
- 静音性重視なら低回転を選ぶ
ケースファンは、前面吸気・背面排気を基本に、バランスよく設置するのがセオリーです。
ファンのサイズは120mmまたは140mmが一般的で、取り付けスペースとの干渉に注意が必要です。
CPUクーラーは高さ制限があるため、大型空冷や一部簡易水冷は取り付けが難しいこともあります。
正圧(吸気多め)と負圧(排気多め)のバランスを考えて、ホコリや冷却性能を調整します。
騒音が気になる場合は、静音ファンやPWM制御を取り入れると効果的です。



冷却は“つければOK”ではなく“位置と風の流れ”が大事
電源ユニット?交換は要リスク評価
電源ユニットの交換は、確かに性能を引き上げる手段ですが、失敗のリスクも高めです。
とくにメーカー製PCであるOMEN 25Lでは、交換の難易度や保証リスクも考慮する必要があります。
- ATX規格に合うかを確認
- 配線コネクタの互換性を見る
- 裏配線スペースの余裕
- 保証が無効になる可能性
- できれば交換せず構成調整
まず、OMEN 25Lが標準のATX電源を受け入れるか、シャシーの大きさと配線ルートを確認しましょう。
多くのOEM電源は専用コネクタを使っているため、換装時に配線が合わないケースもあります。
また、裏配線スペースが狭いと、余ったケーブルをきれいに収められず、冷却の妨げになります。
さらに、分解によってメーカー保証が無効になるリスクも見逃せません。
そのため、できる限り「今の電源で足りる構成」に抑えるのが現実的な方法です。



電源は最後の手段。できれば交換せず設計を
PCIe拡張・I/O?空きスロットとUSB不足の現実
PCIeスロットやI/Oの拡張は魅力的に見えますが、OMEN 25Lでは制限が多く現実的ではありません。
とくに帯域や排熱の問題、そして物理スペースの制約が大きなハードルになります。
- 空きスロットの物理干渉
- 排熱と吸気のバランス悪化
- USB追加でも給電不足の懸念
- 内蔵キャプチャは非推奨
- 外付け機器での代用が現実解
PCIeスロットに空きがあっても、大型GPUが隣接していると干渉して取り付けができません。
さらに、帯域の制限により、内蔵キャプチャなど高速通信が必要な機器は性能が不安定になりやすいです。
USBポートを増やしたくても、マザーボードのピンヘッダが足りなかったり、給電不足になることもあります。
これらの理由から、I/Oや拡張カードは「外付け機器で補う」という考え方が主流になります。
拡張性に限界がある25Lでは、最初から拡張前提で設計しない方が失敗が少ないです。



I/Oは増設よりも“外付けで逃がす”が正解
パーツ別“ここだけ押さえる”要点
OMEN 25Lでのパーツ増設や交換は、細かい仕様の違いや制限を見落とすとトラブルになります。
そこでこの見出しでは、パーツごとの“落とし穴”と“押さえるポイント”だけを簡潔にまとめます。



各パーツごとに「やる前にこれだけは!」という要点を押さえておくと安心です。
- メモリ:混在を避けて安定運用
- ストレージ:熱対策+大容量戦略
- GPU:エアフローと配線に注意
- 冷却:効果が出る位置に追加
- 電源:余裕20?30%で見積もる
- I/O:安定性重視で外付け運用
それぞれのパーツに適した選び方と注意点を知っておくことで、失敗のない拡張が実現できます。
では、パーツごとに見ていきましょう。
メモリ:デュアルチャネル最適化と容量上限の目安
メモリは手軽に増設できるパーツですが、混在構成による相性問題に注意が必要です。
同一規格・同一容量・同一メーカーで揃えると、デュアルチャネルが安定して動作します。
- スロット配列に気をつける
- 同一規格(DDR4/DDR5)で統一
- 同容量・同メーカーで揃える
- 最大容量の仕様を確認
- 混在構成は不安定になる場合も
たとえば、DDR4を使っている場合は、同じDDR4かつ同じ速度のものを選ぶ必要があります。
異なる容量やメーカーの混在は、認識不良や起動不良の原因になることがあります。
スロット配列も重要で、間違った場所に刺すとデュアルチャネルにならず、性能が落ちます。
上限容量は型番やマザーボードによって異なるため、公式仕様の確認が欠かせません。
快適な動作と安定性を求めるなら、規格統一とスロット配置にこだわりましょう。



メモリは揃えて刺す。これが一番の安定策
ストレージ:M.2の発熱対策/ベイ1基想定の容量戦略
M.2 SSDは高速ですが、発熱しやすく、その対策を怠ると性能が下がります。
3.5インチベイは1つが標準のため、大容量1本と外付けの併用が賢い選択です。
- ヒートシンク付きSSDを選ぶ
- ケース内のエアフローも考慮
- 大容量1本で構成をシンプルに
- HDDは外付けが前提
- 外付けは熱と音の分離ができる
M.2はマザーボードに直挿しできるため、省スペースで配線不要というメリットがあります。
ただし、発熱によるサーマルスロットリングが起きると、読み書き速度が急激に低下します。
ヒートシンク付きのSSDや、ケースファンでエアフローを確保する対策が必要です。
3.5インチベイの数が限られるため、大容量SSDまたは外付けHDDで運用する戦略が現実的です。
外付けにすれば、発熱や駆動音を本体から分離できるというメリットもあります。



ストレージは「熱」と「容量」で設計するのがコツ
GPU:推奨サイズ・補助電源・ケース内エアフロー設計
GPUの交換を検討するなら、サイズと電源、そして風の通り道の3点をセットで考える必要があります。
性能だけで選んでしまうと、物理的に入らない、発熱で性能が出ないなどの問題が発生します。
- ケース内奥行きを実測
- 補助電源の形状と本数を確認
- ケーブルは直角に曲げない
- 風が通るレイアウトを意識
- 吸気と排気の干渉を避ける
まず、使用したいGPUの長さを調べて、ケースに収まるかどうかを確認しましょう。
補助電源は6pinや8pin、あるいは12VHPWRなど種類が分かれるので形状を間違えないようにします。
電源ケーブルを無理に曲げると、断線や発熱の原因になるため注意が必要です。
GPU周辺に空気が流れるよう、吸気・排気の方向を揃えるのがエアフローの基本です。
吸気と排気がぶつからないよう、ファンの向きと位置を工夫しましょう。
GPUは「入るかどうか」と「冷えるかどうか」がカギ
冷却:標準構成の把握と追加ファンの効果が出る位置
冷却の効果を上げるには、標準の構成をまず把握し、ボトルネックになっている部分を狙って強化することが重要です。
ファンを増やすだけではなく、どこに付けるかで性能と静音性のバランスが決まります。
- 標準ファンの数と位置を確認
- 吸気・排気の風の流れを整理
- GPU周辺の温度上昇に注意
- CPUファンのエアフローと併せる
- 回転数調整で静音性を確保
OMEN 25Lは、ケースサイズが小さいためエアフローの設計が特に重要になります。
前面吸気・背面排気が基本ですが、ファンが1基だけの場合は風量が足りません。
追加ファンを取り付ける場合は、GPUとCPUの熱がこもる場所を中心に風を通すと効果的です。
ファンの回転数が高すぎると騒音が増えるため、PWM制御や静音ファンの活用も検討しましょう。
冷やしたい場所を狙って、適切な風の通り道を作ることが成功のコツです。
冷却は「量」より「場所」が効きます
電源:消費電力の見積もりと“余裕度”の考え方
電源ユニットの容量は、ピーク消費電力に加えて余裕を持って見積もることが大切です。
ギリギリの電源構成では、安定動作せず突然落ちたり、寿命が縮む原因になります。
- 構成全体の消費電力を調べる
- ピーク時の使用量を想定する
- 20?30%の余裕を加える
- 高効率な電源を選ぶと安心
- 発熱と静音性にも影響する
各パーツのTDP(熱設計電力)を合計し、実際のピーク時にどれだけの電力が必要か見積もります。
その合計に20?30%の余裕を見て、安定動作と将来の拡張をカバーできる電源を選びましょう。
高効率(80PLUS GOLD以上)の電源は熱を抑えやすく、ファンの静音性も期待できます。
電源に余裕があれば、冷却やパフォーマンスにも余裕が生まれます。
電源は見落とされがちですが、実は安定性のカギになる重要パーツです。
電源は「余裕が正義」。ギリギリは失敗のもと
I/O:ハブ/ドック併用での拡張と安定運用
I/O周りの拡張は内蔵よりも、外付けのハブやドックを使う方が柔軟かつ安全です。
特にOMEN 25Lのような拡張性の限られた筐体では、外部機器で拡張する設計が現実的です。
- セルフパワーハブを選ぶ
- バスパワー機器の過負荷に注意
- 重要な機器はPCに直挿し
- Thunderbolt系は帯域が広い
- 外付けで熱とノイズを逃がせる
USBハブはセルフパワー(外部電源あり)タイプを選ぶと、給電不足の心配が減ります。
ストレージやオーディオインターフェースなど重要な機器は、できるだけPC本体に直接接続しましょう。
ThunderboltやUSB-Cドックは帯域に余裕があるため、多用途に使いやすいです。
また、外付けであれば熱やノイズも本体から離すことが
でき、安定性の向上にもつながります。
I/Oは「どこに挿すか」も含めて運用設計を考えましょう。
I/Oは「つなぐ数」より「どうつなぐか」が大事
用途別おすすめ構成(拡張ロードマップ)
OMEN 25Lは拡張性が限定的なモデルですが、目的を絞って構成を考えれば、無駄のないパフォーマンスが得られます。
ここでは「今すぐの快適さ」と「将来の更新」を分けて考え、用途に応じた最適構成の例を紹介します。
何をするかを決めておけば、拡張も迷わず計画的にできます。無駄なパーツを買わずに済みますよ。
- ゲーム用はM.2×2+静音ファン
- 配信編集は外付けI/Oと大容量保存
- GPU更新前提なら電源と空間を温存
自分の使用目的にあわせて、必要なパーツと拡張余地を設計しましょう。
では、3つの代表的な用途での構成例を見ていきます。
ゲーム特化:M.2×2+静音ファンで軽量運用
ゲーム用途なら、まずはロード時間短縮と静音性の確保に注力した構成が効果的です。
不要な重装備は避け、必要なパーツに絞ることで、軽快かつ快適なプレイ環境が実現します。
- システム用+ゲーム用でM.2×2
- 発熱対策にヒートシンク活用
- 静音性確保のためPWMファン追加
- 外付けは最低限に抑える
- メモリはデュアル構成が前提
1本目のM.2 SSDはOS用、2本目はゲーム専用にすることで、読み込み時間を大きく短縮できます。
ゲーム中は発熱が高まりやすいため、SSDにもヒートシンクを付けて温度を安定させましょう。
ファンは静音性を重視して、回転数制御ができるタイプを選ぶと快適です。
外付けストレージや周辺機器を最小限に抑え、配線をシンプルにすると動作も安定します。
メモリは最低でも8GB×2のデュアル構成で、動作のボトルネックを減らすのが理想です。
ゲーム特化なら「早く・静かに・軽く」がポイント
配信・動画編集:外付けI/O+大容量ストレージで安定性重視
配信や動画編集には、容量と安定性が最重要です。
帯域や発熱の観点から、内蔵よりも外付け機器を活用する構成がおすすめです。
- USBまたはThunderboltのI/O活用
- 外付けSSD/HDDで保存容量を確保
- セルフパワーハブで給電対策
- 冷却ファンで安定動作を維持
- 作業用メモリは32GB以上推奨
編集データや録画ファイルはサイズが大きいため、大容量ストレージの導入は必須です。
外付けSSDは転送速度が速く、作業の待ち時間を減らすのに役立ちます。
I/OはUSB3.2やThunderbolt対応の外付けドックを使うと、安定性と拡張性が確保できます。
セルフパワータイプのUSBハブを使えば、電力不足による切断トラブルも防げます。
動画編集ではメモリ消費が大きいため、32GB以上が快適な作業ラインとなります。
編集系は「保存」「安定」「余裕」の3点セットで
将来GPU更新前提:電源余裕・クリアランス確保を優先
今は軽い構成で済ませ、将来のGPUアップグレードを見越した設計をしておきたい方も多いはずです。
その場合は、電源とスペースに余裕を持たせた構成にしておくのがポイントです。
- 今は省電力GPUで運用
- 電源は余裕あるW数を選定
- GPU長さのスペースを空けておく
- エアフロー重視の構成にする
- 配線取り回しを最初に整える
今はエントリークラスのGPUで運用し、後でハイエンドモデルに差し替える前提で構成します。
このとき、電源ユニットは500W前後ではなく、650W?750Wの余裕あるモデルを選ぶのが安全です。
ケース内には、将来入れる予定のGPUサイズ(長さ・厚み)を想定してスペースを空けておきましょう。
吸気と排気の流れを意識し、冷却に適した構成にしておくと将来の発熱にも対応しやすくなります。
電源ケーブルのルートや長さも、最初から余裕を持たせておくと交換作業がスムーズです。
将来GPU強化を狙うなら、「余白」を残して組む
25Lで足りない時の選択肢
OMEN 25Lは手軽でスマートな構成が魅力ですが、用途によっては拡張の限界が見えてきます。
そのようなときには「上位筐体に移行する」か「外付けを前提に構成する」かが現実的な選択肢です。
25Lが合わないと感じたら、上位モデルや外付けでの回避策を考えてみましょう。無理な拡張より安全です。
- 上位筐体で内部余裕を確保
- 外付け運用で柔軟性を高める
ここでは、「40L/45Lへの変更」と「外付け中心の設計」の2つの方向性について詳しく見ていきます。
どちらも「無理なく拡張性を高める」ための現実的な方法です。
40L/45Lとの違い(ベイ数・PCIe空き・冷却余地)
OMEN 40Lや45Lは、25Lと比べて拡張性に大きな余裕があります。
内部スペースや冷却性能、搭載できるパーツの幅が広がるため、構成の自由度が一気に上がります。
- 3.5インチベイが2基以上ある
- PCIeスロットに余裕あり
- 大型GPUも物理的に入る
- 電源交換のしやすさが上がる
- エアフロー設計も自由度が高い
40Lや45Lは3.5インチHDDベイが複数あるため、内蔵ストレージの拡張が容易です。
また、PCIeスロットの物理空間にも余裕があり、キャプチャボードや追加GPUも取り付けやすくなります。
高性能GPUのような長くて厚いパーツも、ケース内に無理なく収められる設計です。
電源交換やファンの追加も、干渉や配線の問題が起こりにくくなります。
初期投資は少し上がりますが、将来的な追加投資を抑えられる「長期的コスパの良さ」が魅力です。
「最初から広めのケース」にしておくと後が楽
外付け優先設計で“拡張の壁”を回避するコツ
どうしても25Lのまま運用したい場合は、外付けパーツを活用する構成に切り替えるのがおすすめです。
熱や電力、スペースの制約を超えて、柔軟に環境を広げることができます。
- 外付けSSD/HDDで保存を分散
- USBドックでポート数を拡張
- Thunderboltで高速I/Oも対応
- セルフパワーハブで給電問題を解決
- 発熱・ノイズも本体から分離できる
ストレージ容量が足りないと感じたら、外付けSSDやHDDで拡張すれば物理的な制限を超えられます。
USBハブやドックを使えば、ポート数不足も一気に解決できます。
高速なデータ転送が必要な場合は、Thunderbolt対応の外付け機器が便利です。
電力不足を防ぐためには、セルフパワー(AC電源付き)のハブを選ぶと安心です。
外付け機器は本体から発熱や駆動音を切り離せるという面でも、安定運用に貢献します。
外付け運用は「限界を超える工夫」として非常に有効
トラブル回避チェックリスト
パーツの拡張や交換は、慎重に行えば快適なPC環境が手に入ります。
ですが、たった一つの見落としで起動不能や動作不安定に陥るケースも少なくありません。
拡張する前に“チェックするクセ”をつけておけば、ミスなく安定運用ができますよ。
- 物理干渉や相性を事前に確認
- OSやドライバは最新状態に
- 温度・消費電力をベンチで検証
ここでは、実際の作業前後に役立つチェックポイントを2つの観点からまとめました。
作業前の「確認」と作業後の「検証」を忘れなければ、失敗のリスクは大きく減ります。
物理干渉/発熱/電力不足/ケーブル長/相性問題の事前確認
まず重要なのは、パーツの取り付け前に「ちゃんと入るか・動くか」を確認することです。
測って、揃えて、配線してテスト。これを丁寧に行えばトラブルの8割は防げます。
- パーツ寸法とケース内スペースを測る
- 干渉しそうな部位(HDD・配線)を確認
- 電源容量と補助電源の形状を確認
- ケーブルが届くか、曲げすぎないか確認
- メーカー公式で相性情報をチェック
パーツの長さ・厚みは、定規を使ってケース内を事前に測っておきましょう。
GPUやファンが、HDDマウントやフロント配線に当たるケースもあります。
電源のW数が不足していたり、補助電源コネクタの形状が合わないと、起動しないこともあります。
ケーブルの長さが足りない・曲がりがきついと、断線や発熱の原因になります。
購入前には、マザーボードやメモリ、GPUなどの相性情報を公式サイトやレビューで確認しておきましょう。
「測る・合わせる・テストする」この3つが基本です
BIOS・ドライバ更新とベンチでの動作検証手順
パーツの取り付けが終わったら、そのまま使い始めるのではなく、動作の安定性を確認する作業が必要です。
特にBIOSと各種ドライバの更新、簡易ベンチマークでの確認は必ず行っておきましょう。
- BIOSは最新バージョンに更新
- GPU・チップセットのドライバ更新
- 設定を初期化して再構成
- 簡易ベンチで動作確認
- 温度・騒音・消費電力を確認
BIOSの更新は、パーツの認識エラーを防ぐだけでなく、最新CPUやメモリへの対応も広がります。
GPUやチップセットのドライバも、古いままだと性能が出ず、トラブルの原因になります。
設定を初期化し、改めて最適な構成を手動で組み直すことで、動作の安定性が向上します。
ベンチマークソフト(例:Cinebench・3DMarkなど)で性能を測って、温度や動作音、消費電力を観察しましょう。
違和感があれば、ケーブル・ドライバ・相性などを一つずつ見直していくのが安全です。
取り付けたら「更新→初期化→確認」で不具合を防ぐ
まとめ:拡張“前提”を理解して選べば、OMEN 25Lは高コスパな選択肢
OMEN 25Lは、拡張性が“必要最小限”であることを理解した上で選べば、非常にコストパフォーマンスの高い1台です。
すべての用途に完璧ではありませんが、「用途に応じて設計する」意識があれば、無駄のない構成が実現できます。
拡張ありきで考えると物足りませんが、「必要なだけ」で割り切れば、OMEN 25Lは優秀な選択肢です。
チェックリスト再掲:
- 型番・世代・電源容量・GPU寸法を事前確認
- 拡張の優先度と目的を明確にする
- 物理干渉・電源・冷却を測ってから選定
- 交換後はBIOS・ドライバ・温度をチェック
- 「今必要な機能」だけに絞って運用する
拡張性を優先したい人は、最初から40L/45Lを検討した方がコスパが良いケースもあります。
一方、静音や省スペースを重視し、必要な部分だけ拡張できればよいという人には、25Lがベストバランスの選択です。
意思決定の分岐イメージ:
- 拡張重視 → 上位筐体(40L/45L)へ
- 運用重視 → 外付け前提の25L活用
- 最低限でOK → 25Lそのままで十分
OMEN 25Lをどう使いこなすかは、「拡張の限界」を知った上で「どこを伸ばすか」を決めることです。
今回の内容をもとに、自分の使い方に合った設計を考えてみてください。
\スペック拡張性を詳しく見る /